はじめに
「子育てしやすい地域はどこだろう?」
これは共働き世帯や転勤・移住を検討する家庭にとって切実なテーマです。
しかし、自治体の発表する待機児童数は「潜在的な待機児童」を含まないため、単純な比較では誤解を招きやすい指標です。
そこで本記事では、こども家庭庁が公開する最新データ(2019~2024年度)を収集・整理し、独自にランキング化 しました。
👉 Tableauを用いて作成したインタラクティブなダッシュボードも用意。
自分の地域や気になる県をクリックして、最新データを直接確認できます。
子育てしやすい都道府県ランキング【2025最新版】
上位グループ:待機児童ゼロの県
すでに 待機児童ゼロ を達成している県が多数あります。
「希望すれば入園できる」安心感があり、子育て世帯には大きな魅力です。
例:鳥取県・島根県・福井県など(詳細はダッシュボードで確認可能)
中位グループ:充足率100%以上の県
北海道や長野県などは、充足率が100%を超える という一見「余裕があるように見える」結果になっています。
👉 充足率の定義
利用定員数 ÷ 申込者数 × 100
- 100%未満 → 申込者に対して定員不足
- 100%以上 → 定員を超えて弾力的に受け入れている状態
⚠️ 注意点:
「100%以上=余裕」ではありません。
- 年度途中での追加受け入れ
- 一時預かり枠の活用
- 0歳枠不足・3歳枠余裕など年齢差
- 都市部と地方部の格差を平均化した影響
これらが重なり、現場の努力によって“何とか”対応している数字 だと理解する必要があります。
下位グループ:都市部に待機児童が集中
東京都や大阪府など大都市圏では依然として待機児童が存在。
特に0〜2歳児クラスは希望が集中し、「入りたい園に入れない」ミスマッチ が大きな課題です。
読み取れること①:待機児童は全国的に減少傾向
国の政策による定員拡大や、認可保育所・小規模保育施設の整備が進んだ結果、全国的に待機児童数は大幅に減少 しています。
地方部を中心に「希望すればほぼ入れる」状況が整いつつあるのは、大きな成果といえます。
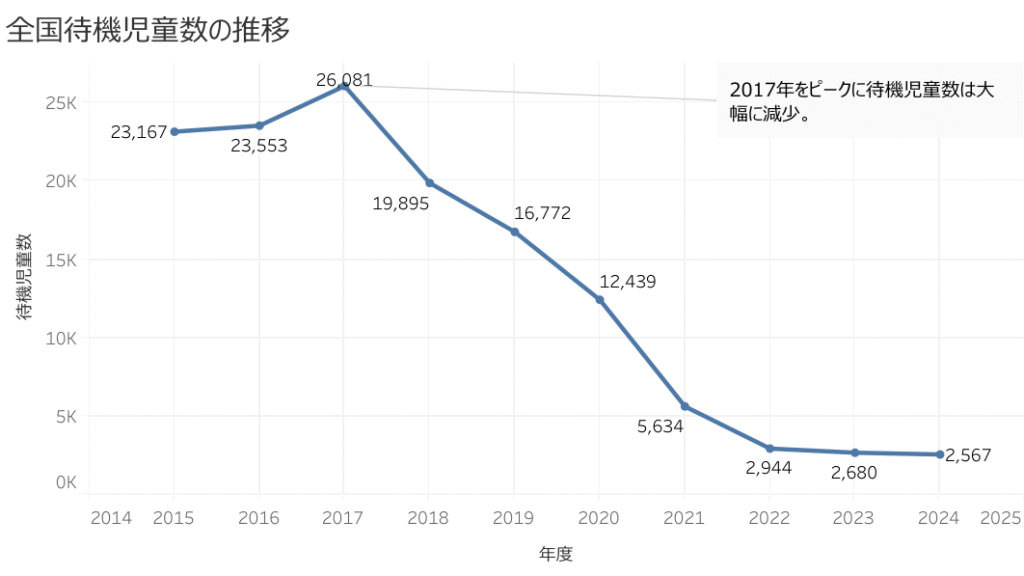
読み取れること②:一方で申込者数は増加
しかし注目すべきは、待機児童が減った一方で 申込者数は年々増加 していることです。
背景には、
- 共働き世帯の増加
- 女性の就業率向上
- 保育所整備拡大による「とりあえず申し込んでみよう」という家庭の増加
があります。
つまり現状は、
「ニーズは膨らみ続けているが、供給も必死で追いついている」 という構図。
このバランスが崩れれば、再び待機児童問題が顕在化する可能性があります。
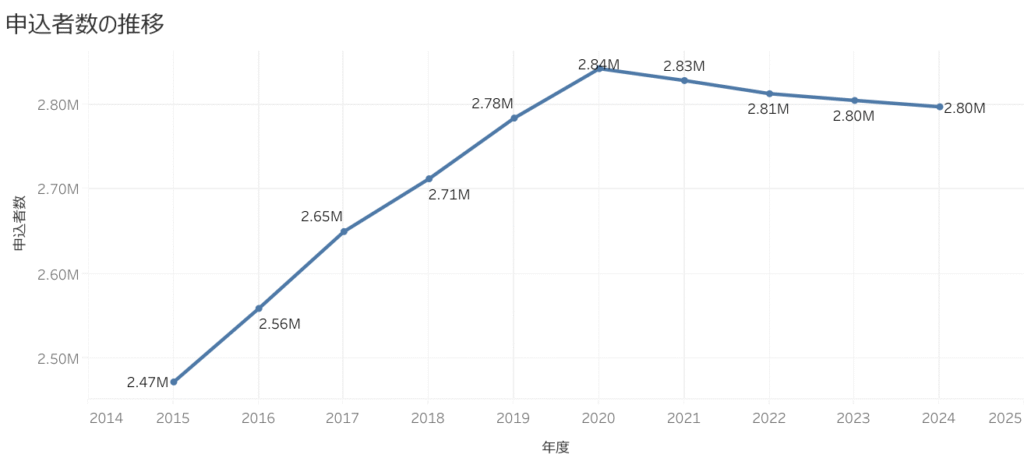
都道府県ランキングで見る地域差
データを俯瞰すると、以下のような傾向が見えます。
- 東京都・大阪府・愛知県など大都市圏 → 待機児童数が依然として多い
- 地方都市 → 充足率が高く、待機児童ゼロ県も多い
つまり「子育てしやすさ」は全国一律ではなく、都市部と地方での格差 が鮮明です。
データの定義と注釈
本記事で使用したデータは、子ども家庭庁「保育所等関連状況取りまとめ」「保育提供体制ダッシュボード」より取得。
- 申込者数:保育必要性認定を受け、入園を希望した児童数
- 利用定員数:自治体が設定した受け入れ枠数
- 利用児童数:実際に保育を利用している児童数
- 待機児童数:申込者から「利用児童」と除外4類型(育休中・特定園希望・求職中・自治体独自事業利用)を除いた数
- 充足率:利用定員数 ÷ 申込者数 × 100
⚠️ データ利用上の注意点
- 市区町村レベルの利用定員数は 2024年度から公開開始 → 充足率は市区町村単位では2024年度以降が正確。
- 充足率100%以上は「余裕」ではなく「弾力運用」の結果。
- 待機児童数は公式定義に基づくが、潜在的待機児童(希望園に入れないケースなど)は含まれない。
まとめ
- 待機児童ゼロ県が増加 → 地方を中心に子育てしやすい環境が整備
- 申込者数は増加中 → ニーズは高まり続けており、政策の継続が不可欠
- 充足率100%以上の県 → 柔軟な現場対応で支えているが、現場の負担は大きい
- 都市部の課題 → 依然として0〜2歳児クラスを中心に厳しい状況
全国的には改善しているものの、「どの地域で子育てするか」によって環境は大きく異なります。
👉 自分が住む地域のデータを確認し、子育てや働き方の選択に役立ててください。
【作成したTableauデータ】
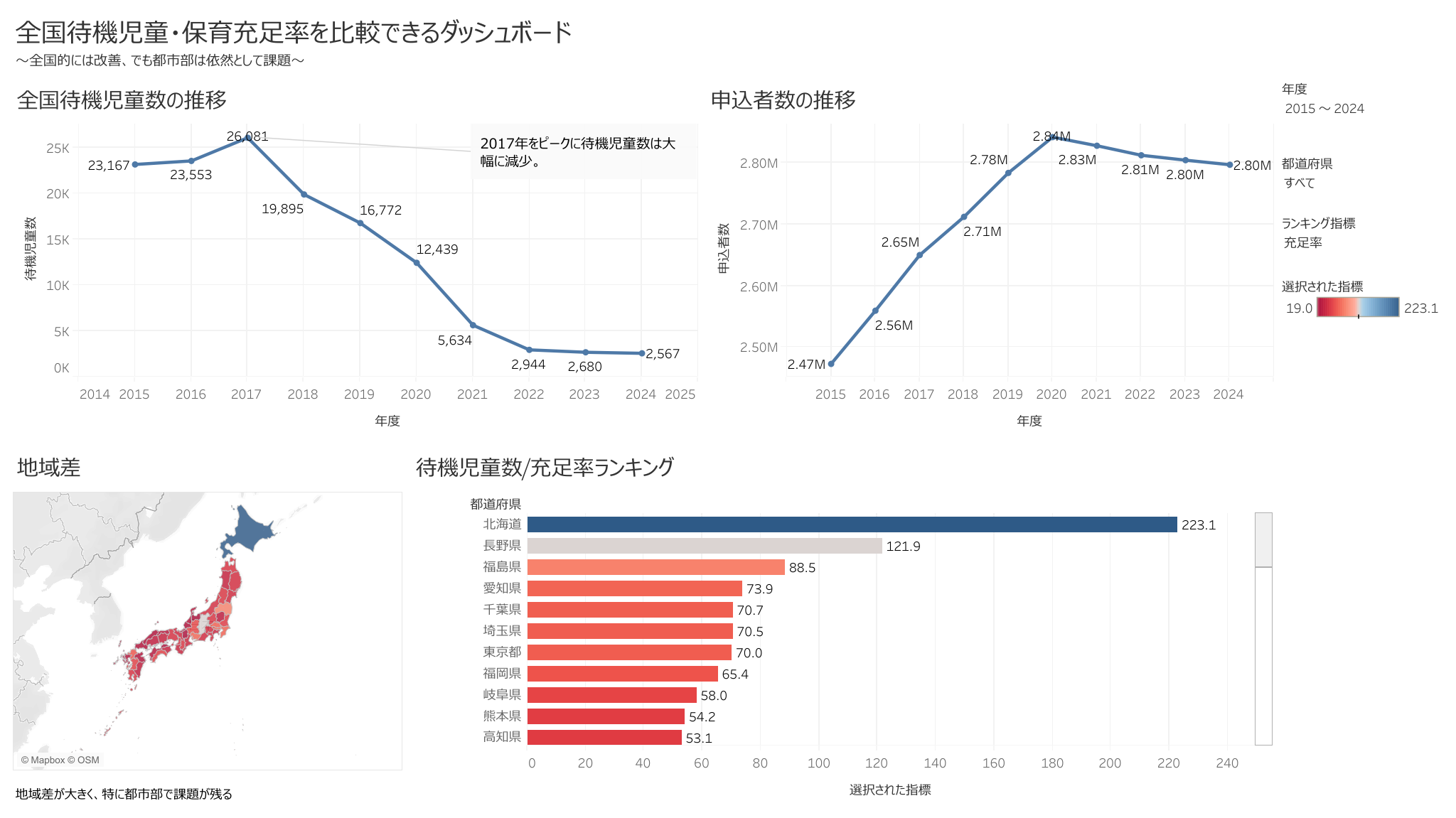





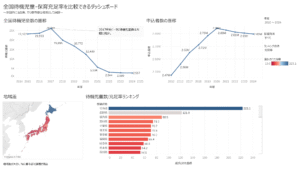
コメント