子どもが着替えなくて悩んでいました。
「早く着ろー!」
この言葉、子どもに何百回言ったんでしょうか。
小さい子供を持つ親なら、この気持ちが分かるはず!
毎回、こんな感じだと結構イライラたまりますよね。。。
風呂あがり、朝起きて着替えるとき、なぜか子どもがいきなり脱ぎだした時・・・。
試行錯誤を繰り返しながら、ようやく一つの解決策を見いだしましたので共有します。
息子は今、3歳ですが、この解決策を見つける前は本当に自分で着替えませんでした。
本当は自分一人で着替えられる能力があるはずなのに、
「一人じゃ着替えられなーい」
「このシャツ、後ろ前分からなーい」
と、こんな感じででした。
なぜそうなる・・・!
こういう人にオススメの記事です!
- 未就学児がいる家庭
- 子どもが、自分から進んで着替えをしない
- 子どもの自主性を伸ばしたい
- あらゆる場面で、子どもが自分で選択できるように育てたい
- 共働きで、朝の時間的猶予が無い
- 子どもにチャッチャと行動してもらいたい
<yamato家プロフィール>
- 夫婦そろって、フルタイム共働き
- 2020年7月現在、息子3歳(保育園)、娘6歳(小1)
- 夫婦の実家は遠方のため、頼れない
- 息子を0歳6ヶ月から保育園に預けており、プロ保育園児
- 子どもが自立できるように育てたいと思っている
- 自由に、のびのびと子育てがしたいと考えている
子どもに着替えにかかる時間を聞くだけでよい!

結論から申し上げると、
着替えにかかる時間を本人に決めさせるだけ。
これだけで、子どもが自分で着替えるようになります。
騙されたと思って、やってみてください。
着替える時間を子どもに決めさせるだけで着替えるようになるのか。
ポイントは、子どもが「自分で決めた」というところです。
親に早くしなさい!とか言われても、たぶん子どもは言うこと聞きません。
なぜなら、我々大人は時間が刻一刻と流れていることが当たり前の環境にいますが、
子どもは時間なんて気にしません。
急ぐ理由もございません。
しかし、大人には子どもに服を早く着替えてもらいた様々な理由がある!
では、どうすれば(急いで)着替えてくれるのか。
我が子を色々と観察していると、一つのことが分かりました。
それは、自分で決めたことはちゃんとやるということ。
逆に言えば、親が決めたことは基本的に言うこと聞きません。
「○○(子の名前)なら、お着替え何分で出来る!?」
「早く着替えなさい」と子どもに言ったところで、あまり意味はありません。
それよりも、着替えをするということを前提にし、その着替える行為がどのくらいでできるのかという作業時間を本人に決めさせる。
また、この何分かかるのか?というのも、
実際にタイマーなどで測ってあげましょう。
うちは、Googlehomeがあるので、「オッケー、Google、2分測って!」といえば、
息子は急にバタバタし始めます(笑)
2分以内に着替えられたら、ニコニコの顔で、
「オッケー、Google、あと何分?」と問いかけています。
ゲーム感覚で、2分以内に着替え終えて、あと何分残っているのかを子どもは楽しんで確認します。
どうだ、自分は、自分で設定した時間よりも早く着替えることができたんだ!と。
基本的に、子どもは自分で何かを決めることが大好きです。
子どもの楽しみな選択という行為を親が奪ってはいけません。
可能な限り選択する行為を奪うことがないように、うちではその日の服やテレビを見るタイミングなど全て選ばせてあげています。
「そうは言っても、うちの子は決められない子なんです」という意見もあるかもしれません。
しかしながら、ずっと決められない状態が続き、
(ましてや、3歳でどれくらいの時間がかかるのかくらいは決められるのですから)
そのまま大人になってしまうことは本当に恐ろしいことだと思います。
実際に、子離れ出来ない親・親離れ出来ない子どもも結構周りにおりまして・・・。
皆さんのまわりにもいらっしゃいますか。。。。
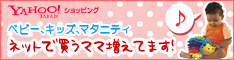
人生は選択の連続!

人は毎日、何かしらの選択を繰り返して生きています。
子どもが大人になったら、一緒に何かを選択するのを手伝ってあげるなんて無理です。
就職先を選ぶとき、
結婚相手を選ぶとき、
いずれは全て自分で決める必要があります。
そう考えると、親がしてあげられることというと、
子どもの選択力(判断力)を伸ばしてあげることくらいではないでしょうか。
仮に親から見ると判断結果が間違っていると思っても、
その失敗が、次の判断の時に生きてくると思います。
「だから、あの時ああ言っただろう」は禁句だと考えています。
まとめ
最後は真面目な話になってしまいました。
では、まとめです。
- 子どもは選ぶのが大好き
- 自分で決めたことは 自分ですすんで やる。
- 親は子どもの判断力を養ってあげるため、選ばせてあげるべき
意外に効果ありますよー。
すぐに実践できるので、一度お試しあれ。







コメント